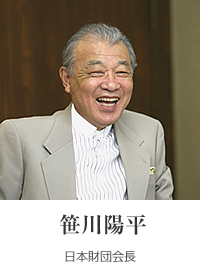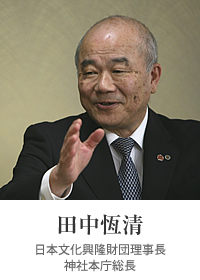コラム
「みんなの鎮守の森植樹祭」座談会
平成27年2月5日
当財団では、東日本大震災により失われた鎮守の森を再生し、地域のコミュニティーの復活を目指そうと「みんなの鎮守の森植樹祭」を平成24年6月の宮城県亘理郡山元町・八重垣神社を皮切りに東北各地の被災神社で展開しております。この事業は日本財団の地域伝統芸能復興基金から支援をいただき、当財団が事業運営、神社本庁などが後援し、鎮守の森の再生を通して、地域のお祭りや伝統文化の復活、鎮守の森と地域の方々の心を繋ぎ止めることを目標に実践している東北支援プロジェクトです。本事業について、日本財団の笹川陽平会長、当財団の田中恆清理事長(神社本庁総長)、第1回植樹祭開催神社の宮城県亘理郡山元町・八重垣神社の藤波祥子宮司から話しを伺いました。(司会・高清水有子)[収録:平成25年3月21日神社本庁]

- それぞれのお立場で、神社や鎮守の森をどのように捉えられているかを伺います。笹川会長からお願いします。

- まず、不幸な大震災でメディアが報じたのは「絆」というキーワードでしたが、絆とは一体何なのだろうかと考えると、日本人にとって絆の原点は神社にあります。鎮守の森で五穀豊穣の感謝、奉納のお祭りなどをすることで、祖父母から孫へと踊りや笛、太鼓などが伝承される。すべての人が役割を持って神社に集まり地域のコミュニティーが強固になってきた。そういう絆のルーツを理解していただきたいと思っています。その意味で現地のみんなが植樹に参加し、共同作業の結果、10年、20年後に一つの形ができていく、そういう経過が重要だと思います。もう一つは、神社がいかに我々の長い歴史の中で重要な位置を占めてきたかを、もう一度、国民に知っていただきたい。そういう二つの思いで支援を始めさせていただきました。

- 田中理事長はどのように捉えていますか。

- 何かあればそこに集い相談し合い、あるいは村の祭りを継承して地域社会を活性化していく。鎮守の森はそういった大きな役割を果たしてきました。したがって鎮守の森が失われることは、日本人にとって存亡の危機だと申し上げてもいいと思うのです。これからも我々は鎮守の森を守るための諸施策に取り組んでいかねばならないと思っています。

- 藤波宮司さんはいかがでしょうか。震災後の鎮守の森についてお聞かせください。

- このたび社殿も鎮守の森も、それこそすべてをなくしてしまったわけですが、何よりもやはり神道は森だろうという気持ちがあります。緑のある空間がないと心が癒やされません。ですから、まず鎮守の森だと思いました。

- 震災から二年という歳月が流れましたが、神社の被災状況の概略を田中理事長からご説明いただけますでしょうか。

- 神社本庁包括下の神社では、被害地域が1都15県に及び、およそ4600社に何らかの被害があり、社殿の全壊等は約300社あります。また亡くなった神職が8人おられ、未だ行方不明の方もおられるということです。この300社に加え、今、我々がたいへん苦慮しているのは、原子力発電所の事故で立入りなどが制限された場所におよそ250社が鎮座していることです。神社界にとっての本当に大きな打撃は、鎮守の森が全壊してしまったこと、すなわち氏子区域が壊滅してしまった地域がたくさんあること。これがやはり大きな課題だと感じています。

- 日本財団の復興支援、とくに地域伝統芸能復興基金(通称・まつり応援基金)の事業において、被災地で鎮守の森を再生させる意義を笹川会長はどのように捉えておられますか。

- 被災地はもう荒寥たる風景です。そのような中で、神社のあったところに木々が育ち、目に見えて青々となっていくのを見れば、被災した人たちも心が和むのではないかということが一つ。もう一つは、まつり応援基金をつかって必要な道具を整備し、とにかく元気を出してもらわねばならないということです。重ねて申し上げますが、日本人の精神のふるさとは神社にあるわけですから、そこをきちっとしないことにはほかが進みません。

- 八重垣神社での植樹祭、氏子さんの受止め方はいかがでしょうか。

- 神社はどうなるのだろうという不安の中でしたが、植樹祭をおこなったことで「ここに神社が戻ってくるんだな」と皆さんほっとなさっている感じがしました。笹川会長さんが言われたように、心のふるさとが神社でしたので、とても喜んでいただけました。
森の木々に思いを託し

- 笹川会長には幼少の鎮守の森の思い出がありますか。

- それはもうみんなが集まる場所ですから。いいことも悪いことも……、鎮守の森に行かないといたずら小僧にはならないですよ(笑)。そんなむちゃくちゃなことはしませんが、そういう少年時代を過ごすことでみんな体力もつくし、精神的にも成長する。そしてふるさとというものがそこに残っていくわけです。

- 被災地では、そういう思い出の木がすべて流失してしまった神社もあるわけですね。植樹祭の重要性は被災された皆さんも強く感じていらっしゃると思いますが、実際にはいかがですか。

- それぞれに思い入れがある木があったと思います。今回、大勢の方に木を植えていただきましたが、その後、「あ、これ私の木?」「ちゃんと育っているかしら」と、何か楽しみにしてお参りしてくださるのですね。これからまた新しい思い出の木ができていくのかなと思って、私も楽しみです。

- 田中理事長は植樹祭を振り返って、いかがでしょうか。

- 最初の植樹では、地元の皆さん方がまだ落ち着いていない状況の中で、果たして協力を得られるのだろうかと少し不安に思っていましたが、その予想は外れました。当初の募集人数以上の人が来られ、本当に驚きました。そして、皆さん熱心に植樹の監修をされた宮脇昭先生のお話に耳を傾けていました。そして、先生のお話のとおり一本ずつ丁寧に植えていかれる。その姿を見ていて、やはり笹川会長が言われたように、植樹はみんなの力でやらなければならないと感じました。自分たちが経験した苦いことをその木に託し、健やかに伸びていく木々を見る。そういう気持ちで皆さんの心が結集すれば、これほどのことはないと思います。

- この植樹祭は、木の専門家である宮脇昭先生が監修されていますが、先生の存在についてはいかがでしょうか。

- 私は平成9年に宮脇先生と初めてお目にかかったのですが、米国のハーバード大学で「神道とエコロジー」というシンポジウムに参加した時のことです。その中で、宮脇先生は「鎮守の森を世界の森に」ということを言われました。「鎮守の森」が世界を救う、ぜひこれを世界用語にしたいとまで述べられたのですが、お聞きすると、今や世界的に通用する言葉らしいですね。宮脇先生の行動力は本当にすごいと思います。
森が育む文化を守り伝えるため

- 世界には、鎮守の森のような存在はあるのでしょうか。

- ありませんね。私どもは古くからあちこちの小学校などで植樹運動をやっています。私は世界120ヵ国を歩いていますが、日本人ぐらい木を愛する国民はいません。パリに行くと緑が多いと言いますが、日本は桁が違う。日本では各家庭でも木を大事にして植えているでしょう。これは皇室におかれても全国植樹祭にご出席いただいているわけでして、もっと国民運動として広げていく必要があると思っています。

- 今後の神社復興に関する懸念事項についてはいかがでしょうか。

- 被災地には何度も入りましたが、境内地のすべてが流された神社の若い宮司さんは、地域に誰もいなくなった中で、いろんな芸能が奉納される毎年一回の村祭が途絶えたら神社の信仰は途絶えてしまうと心配されており、神社を建てる前にまず地域の伝統芸能を復興しますと語られました。仮設住宅では氏子地域の方々が一緒だとは限らないので、連絡のとりようがない。一年あるいは二年、伝統芸能や神事が途絶えたら、次は本当に繋がっていかないのではないかという危機感を持っておられるのです。
日本の誇りを取り戻すため

- 近年、神社や鎮守の森に関心を持つ日本人が増えているようです。その点についてはいかがでしょうか。

- 神社は今までも親しまれています。ですが、被災地に限らず全国的にもう一歩踏み込んで神社と国民のあり方を深めてほしいと思います。これは世界に誇るものです。我々日本人は、自分の優れたことを忘れてしまった。進歩的文化人という人は日本の悪口ばかり言います。ですが、世界中どんな貧しい国の人でも自分の国に誇りを持っています。世界に誇るべきものが日本に幾つあるかわかりませんが、世界一多いのではないですか。鎮守の森にしてもそうだし、料理にしても、山の緑にしても、春夏秋冬にしても、日本人はこんなにもすばらしいところに生活しているということを知らないのですね。

- なるほど。神社という存在、鎮守の森という存在も日本独特であると。田中理事長はどのように感じられますか。

- まったくおっしゃるとおりです。日本に誇りを持たないで、これからの日本はどうなっていくのかと私どもも心配です。とくに若い人たちにそういった気持ちを昂揚させなければ、国の将来はひじょうに危ないと感じています。その中で神社の果たすべき役割は大きいと思いますし、日本人がずっと育て、継承してきたものを、我々はこれからもしっかりと伝えていくための取組みをしていかなければならないと思います。神道には教義がないとよく言われますが、世界でも珍しい宗教だと言えるでしょう。ですが、だからこそ二千年も三千年も続いてきたのだと思うのです。そういう意味では、これからは誇るべき信仰観も世界に向けて「日本を見習いなさい」ぐらい言っても、罰は当たらないのではないかと思うのです。

- おっしゃるとおりです。例えば今度の震災でもね、食料を待つ列の後方に並んでいた子供に食料をあげたら、自分で食べずに一番前の配給場所に届けに行ったという話がベトナムを中心に流れ、彼らは涙を流したそうです。世界中の人が「何で日本人はこんなに規律正しいのか」と言いますが、大体、規律はどこの国でも宗教から来ています。今、道徳教育がないにも拘らず、日本の子供たちの中に残っているこういうものは、みんな神道から来ているのです。そのルーツを我々は誇りに思わなければ。
引き継ぐ責務果たすために

- それでは結びに改めて今後の植樹祭への意気込みを頂戴できますでしょうか。

- 先ほども申し上げましたように、神社・鎮守の森が日本人のルーツであり、それを誇りに思って引き継いでいく責任があるということを再確認していただきたい。私たちの支援は被災地だけに限っておりませんから、日本全国どこでも、神社に奉納する伝統芸能に必要とするところがあれば、これからも引き続いてご支援をさせていただきたいと思っています。

- 神社は地域の方たちにとって欠かせない場所であり空間であり、そこに伝わる伝統芸能などが今後も継承されていくことが理想的です。そのことを私どももさまざまな角度から取り組んでおりますが、なかなか現実には厳しいものがあります。しかし、これは手を緩めるわけにもいきませんので、今後とも笹川会長のご協力を得ながら、取り進めてまいりたいと思います。

- 本日は、どうもありがとうございました。
地域伝統芸能復興基金(通称・まつり応援基金)日本財団の姉妹財団である日本音楽財団からの寄付金をもとに設置された基金。東日本大震災救援に協力するため、国際オークションで売却したヴァイオリン(ストラディヴァリウス1721年製)「レディ・ブラント」の売上金約11億6800万円が基となっている。日本財団では楽器の売却代金であることを踏まえ、伝統芸能の復興に寄与することを目的とし、各種支援活動を展開している。
これまでに実施した植樹祭

第1回 八重垣神社(宮城県亘理郡山元町)
開催日 平成24年6月24日 参加者数 約550人 植樹本数 3,238本

第2回 吉田浜神明社(宮城県亘理郡亘理町)
開催日 平成24年8月14日 参加者数 約250人 植樹本数 1,118本

第3回 青巣稲荷神社(宮城県亘理郡山元町)
開催日 平成25年4月29日 参加者数 約350人 植樹本数 2,448本

第4回 川口神社(宮城県亘理郡亘理町)
開催日 平成25年5月3日 参加者数 約250人 植樹本数 1,811本

第5回 鳥海塩神社(宮城県亘理郡亘理町)
開催日 平成25年7月7日 参加者数 約550人 植樹本数 2,123本

第6回 伊去波夜和氣命神社(宮城県石巻市大宮町)
開催日 平成26年4月6日 参加者数 約350人 植樹本数 3,650本

第7回 見渡神社(福島県いわき市久之浜)
開催日 平成26年4月27日 参加者数 約280人 植樹本数 790本

第8回 新山神社(宮城県石巻市雄勝町)
開催日 平成26年5月3日 参加者数 約200人 植樹本数 2,800本

第9回 五十鈴神社(宮城県石巻市雄勝町)
開催日 平成26年7月6日 参加者数 約450人 植樹本数 2,500本